お問い合わせContact
仏事に関するご質問やお問い合わせを受け付けております。

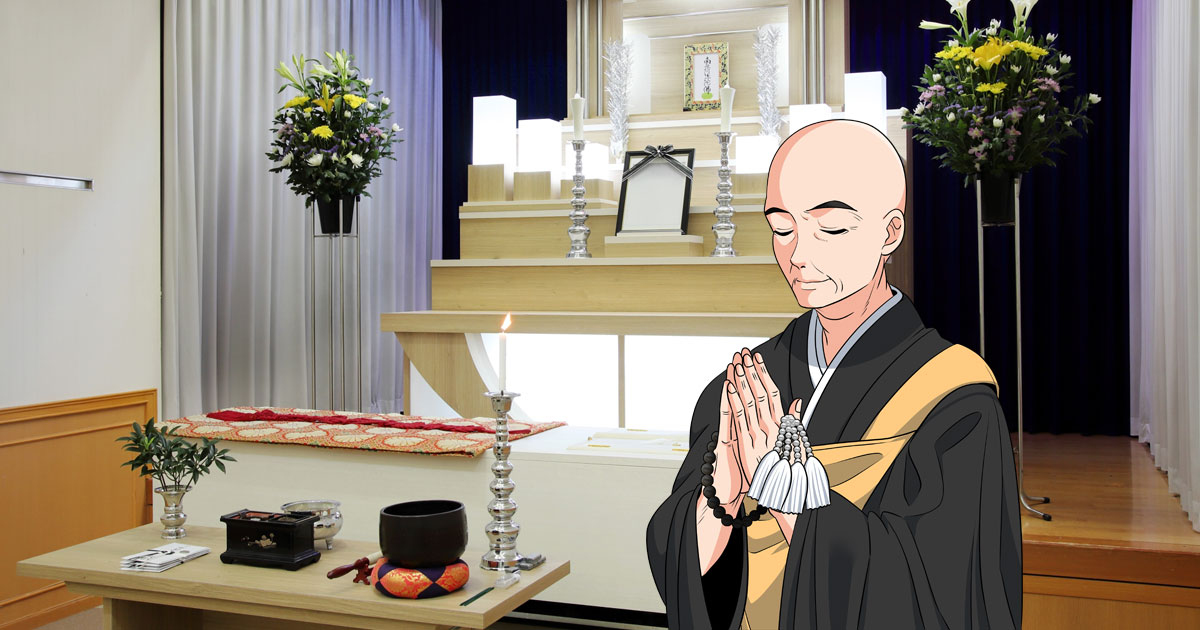
私(住職)はお通夜の時、親しい方の死のご縁を通して、忘れていた大事なことを思い出していただきたいと思い、いつも同じお話をさせていただいております。
親鸞聖人が88歳の時、常陸国(現在の茨城県北東部)北部の奥郡に住んでいた乗信房に宛てて、お手紙を書いておられます。親鸞聖人87歳・88歳の2年間は全国的な大飢饉がありました。奥郡は歴史の浅い開拓農村で、経済基盤が非常に浅いため、飢饉の被害を最初に受けたのです。
なによりも、去年・今年、老少男女おほくのひとびとの、死にあひて候ふらんことこそ、あはれに候へ(『親鸞聖人御消息』)
「去年から今年にかけて、老人・若者、男・女と言わず、随分たくさんの人が次々と亡くなり、まことに哀れなことでありました」と書き始めています。飢饉で多くの人々が亡くなり、食料を求める流民があふれ、さらに道端で亡くなっていきます。汚い環境の上に栄養不足のため、流行病がまん延します。こうして、人口が3分の2から半数ぐらいに減ったといわれる大変な時代でした。
ただし生死無常のことわり、くはしく如来の説きおかせおはしまして候ふうへは、おどろきおぼしめすべからず候ふ。(『親鸞聖人御消息』)
親鸞聖人は「生まれてきたものが死ぬことは驚くことではない。いつ死んでもおかしくないものが、今、生きている。それを不思議と言うのだよ。みんなは死ぬことに驚きすぎて、今、生きている"いのち"にであってないじゃないか」と言われます。
この言葉によって、生と死から目を背けるのではなく、いつ死んでもおかしくない"いのち"は本来どうあるべきものなのか、"いのち"終えるとはどうなることなのかと一度しっかりと見つめ直すことが大切なのです。
しかし、私の中では、生と死は反対の概念であり、生きていることがすばらしいと思えば、死ぬことはつまらないとしか思えません。この生と死を意味づけることができるのは、生と死を超えた悟りの世界の言葉を聞くことしかないのです。
阿弥陀さまのご本願には「生きとし生きるものよ。本当に疑いなく、私の国、お浄土に生まれると思って、私の名、南無阿弥陀仏を称えてくれ。もしそのものがお浄土に生まれないようならば、私は仏にならない」と言われています。
私は、この言葉を分からないまま「南無阿弥陀仏」と如来さまの願いを受け入れます。すると、阿弥陀さまは「あなたは、私のかけがえのない仏の子だよ」と言われます。その時、はじめて自分の"いのち"にであうのです。私は私しか生きようがない"いのち"を生きているのです。そして、死ぬとしか思えなかったことが、お浄土に生まれて阿弥陀さまと同じ悟りの身にすると言われるのです。阿弥陀さまに目覚めをうけながら、お浄土をめざしてこの人生を生きるという新しい方向が与えられるのです。
死に別れることは寂しいことです。しかし、その死を通して、おかげですばらしいことをありがとうといえる世界が開かれるのです。